「新規事業の立ち上げ」「既存事業のグロース」
組織は今新たなフェーズを迎えています。
あなたが中心となって、事業を動かしてみませんか?
大手からベンチャーへの転職座談会
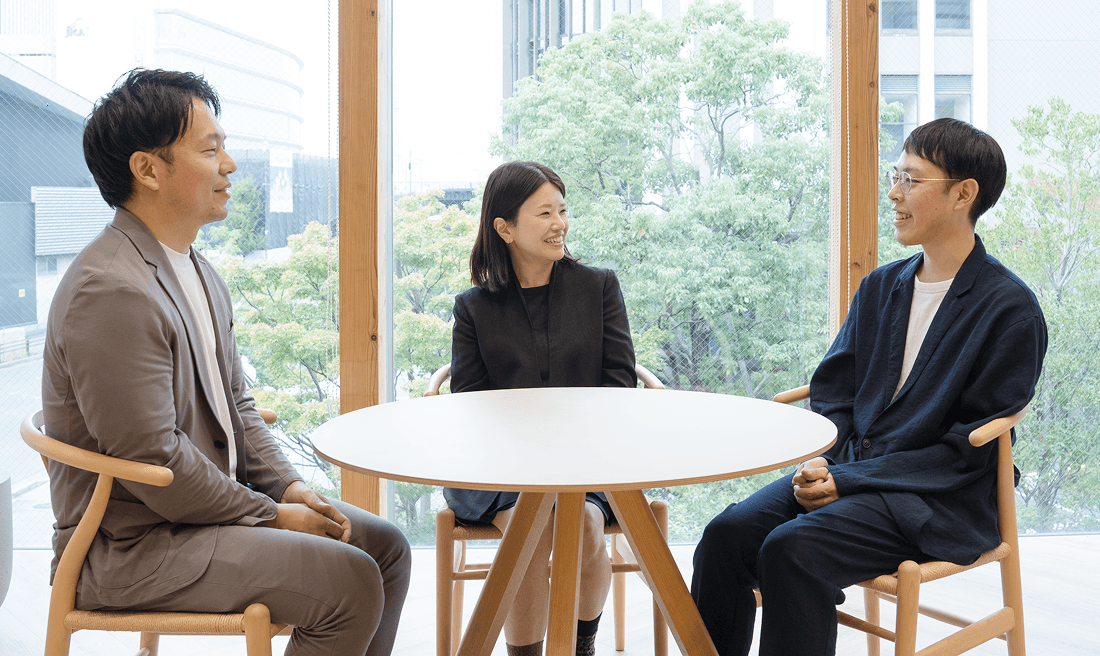
Introduction
世界的に有名な企業や業界トップ企業、歴史の長い老舗企業など、スタメンには大手企業出身の社員が多くいます。彼らはなぜスタメンで働きたいと思ったのでしょうか。転職時の不安や入社後のギャップ、スタメンの魅力などを転職組3名に聞きました。
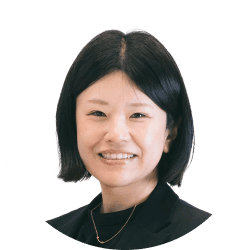
天野 絵里佳
CS第1部 部長
大手自動車メーカーで約13年間、人事領域でキャリアを積む。中でも組織開発や人事制度企画に長く携わり、2023年スタメン入社。新規事業におけるカスタマーサクセス業務の策定・構築から実施に携わり、2024年から現職。

阿部 平
法人営業第2部
新卒で繊維専門商社に入社以来8年間、輸出入業務を軸に国内外の取引先を回る外勤型営業に従事。2022年、フィールドセールスとしてスタメンに入社。エンタープライズ企業を中心に担当し、2024年から現職。

髙原 和人
経理部
大学で農学系を専攻し、製菓・製パン企業に新卒入社。4年間の品質管理業務を経て、経理部に転属。成長戦略に基づくM&Aや月次決算などの業務に従事後、2023年スタメン入社。現在経理部で法的開示などのIR業務にも携わる。
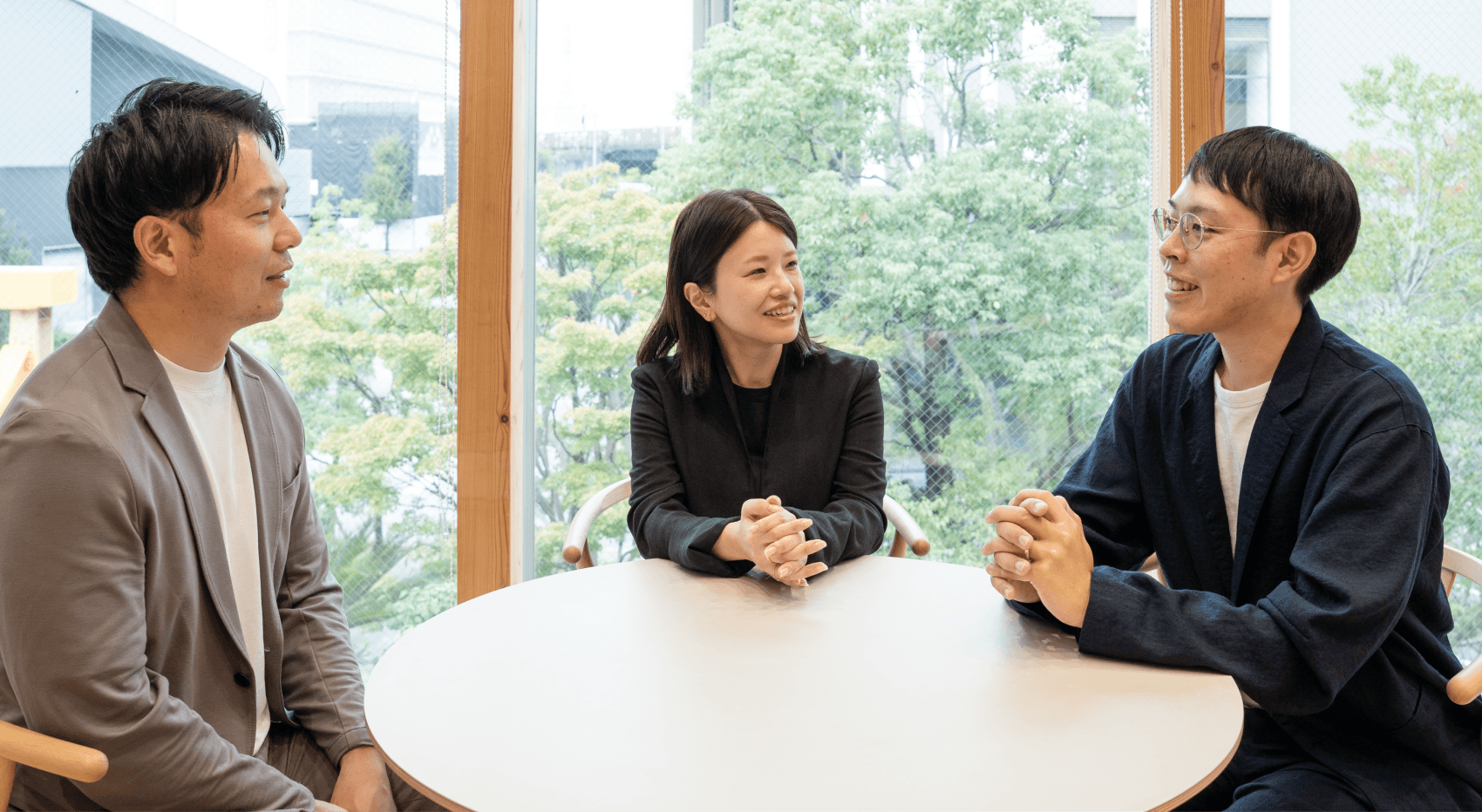
阿部:業界を変えようというのが転職のきっかけでした。それまでいた繊維業界も会社も歴史が長く、成長というよりは生き残りをかけて戦うという雰囲気でした。だからまったく反対の、若くて成長フェーズにある業界や会社で勝ち抜いて進むような仕事をしたいと思ったんです。
天野:私は前職で人事や組織開発に携わっていたのですが、大きな組織を動かすことはすごく大変なんです。やりがいもあったけれど、やりきれなかったこともたくさんあって。その都度どうやったら壁を乗り越えられるのだろうと考えていました。
でも、1社の経験しかないとひとつの方法しか知らない。他にもっといいやり方があるかもしれない。それを知るために違う組織に飛び込んでみようと考えたのが転職のきっかけでした。
高原:僕は前職で6年間ほど経理部にいたのですが、M&Aや月次決算など経営に関わる重要な業務に携わらせてもらったことで、上場企業の経理をやってみたいと思うようになったんです。転職活動を始めたところ、スタメンで経理スタッフを募集していると紹介を受け、転職することになりました。
高原:僕は前職でTUNAGを利用していました。TUNAGはすごく魅力的なプロダクトだと思っていたし、いろいろな人から「スタメンはエンゲージメントを大切にしている会社だ」とも聞いていました。その上、スタメンのIR情報を見て利益を出しやすいビジネスモデルだと分かり、さらに魅力を感じました。
天野:私は転職サイトです。「前職と正反対の規模で、経験を生かせる業務内容」と検索して出てきたのがスタメンでした。“人と組織”がスローガンに掲げられていて、私の経歴にど真ん中で合致しているという点が、スタメンに興味を持った最初のポイントでした。
阿部:私は「名古屋で働く」と決めていたので、Youtubeで名古屋のベンチャー企業を調べていたところ、“東海地区のスタートアップを応援する”チャンネルでスタメンが紹介されている番組をみたんです。
高架下に社屋があるなんて変な会社だなと思ったし、当時の僕には価値観としてなかった“エンゲージメント”ということを軸に会社が伸びている。すごく不思議に思ったけれど、その新しい価値観にものすごく引かれました。
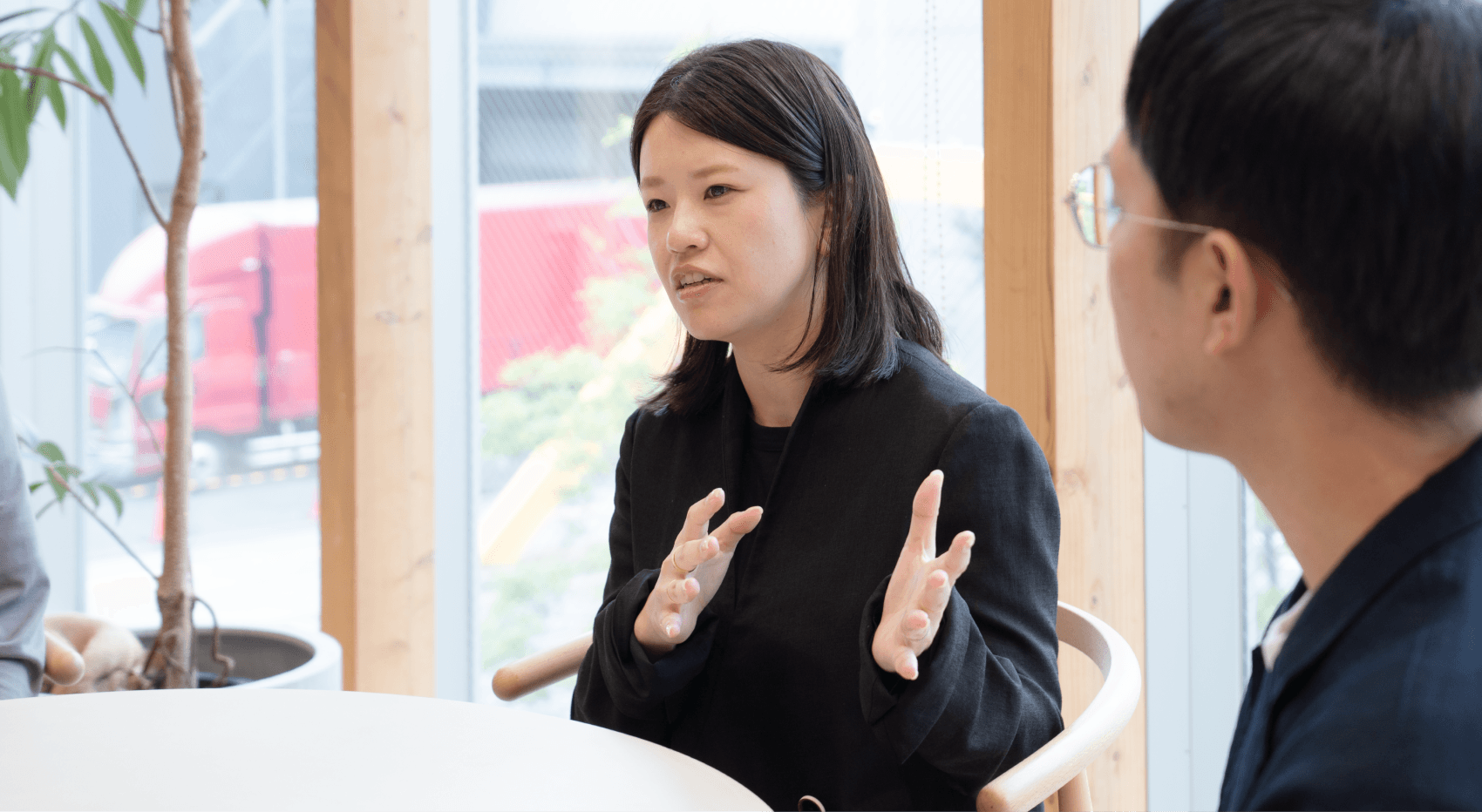
天野:私はあまりなかったです。でも、前職の同僚や上司から心配するような言葉はありました。一般的にはそう思うかもしれないけれど、私には自分なりの勝算というか、スタメンに賭けてもいいと思えるものがあったので、不安はなかったです。
高原:僕も不安はなかったんですが、最終面接で社長の大西さんに「前職よりも売上規模も小さく従業員数も少ない会社だけれど大丈夫?」と聞かれたんです。まずそれをストレートに聞かれたことに驚きましたし、そこまで考えてくれているのだと心に染みました。また、僕自身はみんなで協力しながら会社を大きくしていきたいという気持ちがあったので、「一緒に頑張りたい」と思わせてもらったのを覚えています。
天野:今の話を聞いて、私も声を掛けてもらったのを思い出しました。「前職を続けてもきっと良い道があるはずだけどいいのか」と問われたのです。会社にとって採用活動中にそういった質問をするのはとても勇気がいることだと思いますが、それでも踏み込むのは、人と会社のカルチャーマッチを重視しているからだと感じました。
高原:それ、分かります。僕はカジュアル面談として当時の財務経理部長と居酒屋で面談させていただいたんですが、業務内容や社長の人柄も含めて、僕の希望とマッチしそうだねといったことを親身になって話してくれたのを覚えています。この人たちと働きたいと思ったエピソードのひとつですね。
阿部:入社前から親身になってくれるというのは、僕も経験しました。実は転職のタイミングと子どもの誕生が重なったんですが、「家族のことを大事にしてほしいから、働き方を相談したい」「家族も含めて“転職して良かった”と喜んでもらえるように考えよう」と言われ、不安どころか逆に安心感がありました。
天野:親身になる姿勢は今でも変わっていないですよ。今私は部長として求職者との面接やその後のコミュニケーションを行っていますが、スタメンを選んでもらうか否かに関わらず、目の前の求職者が一番良い選択をできるようにと考えています。
一緒に採用活動を行っている他のマネージャーたちも同じ気持ちだと思います。だから嘘もつかないし、聞きたいこと全部聞いていいよと情報を全てオープンにした上で「自分の意思で決めてほしい」とアプローチしています。
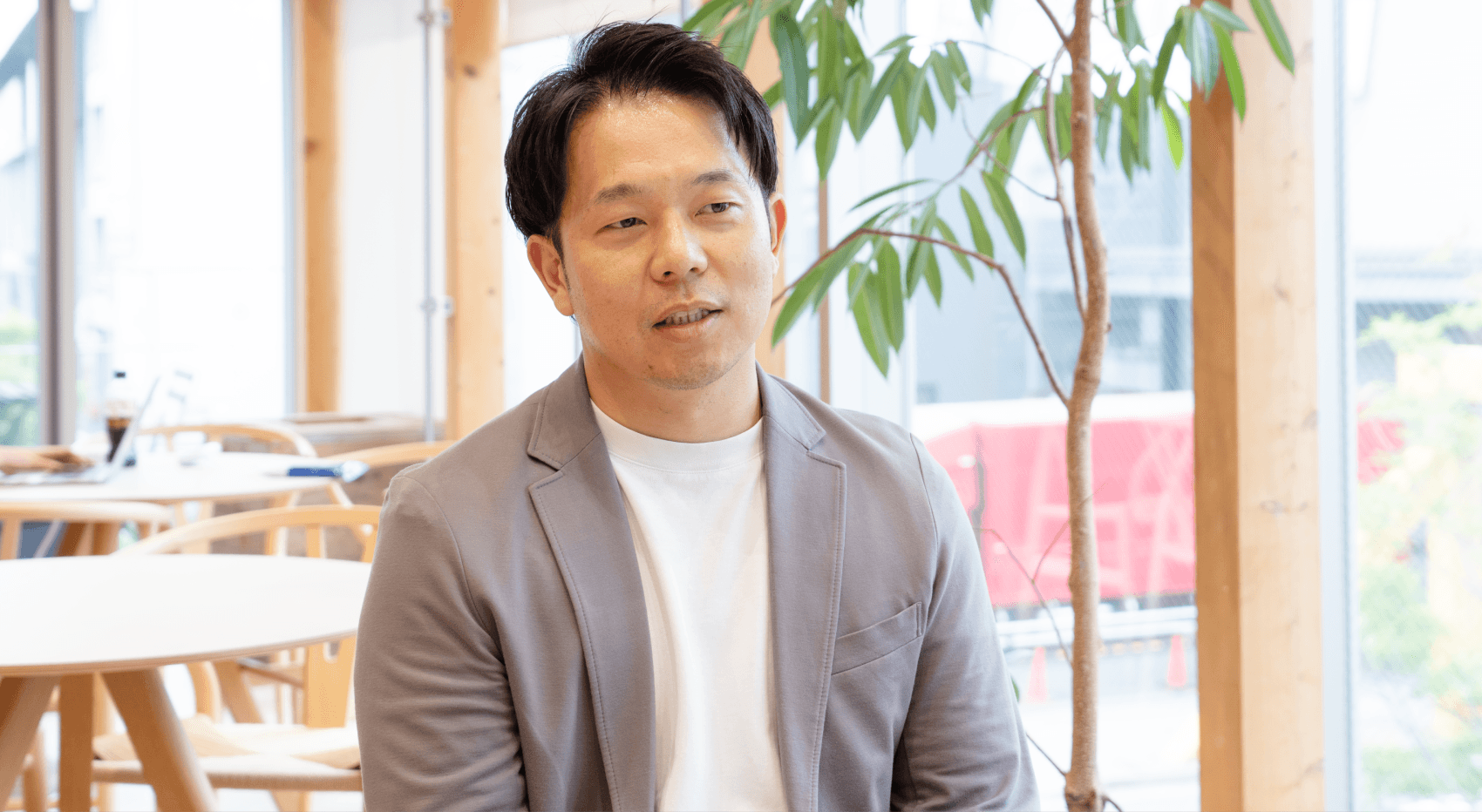
阿部:営業のケースで言うと、前職は業界では社名が通じていたので「知らない」と言われたことはなかったのですが、そこが全然違う。スタメンは業界では知られていても、他での認知度はまだまだだから一層、営業力が問われるし、自分という人間の印象が会社の印象に直結するので背負っているものが違うと実感しています。
ただそれは予測していたギャップです。会社の名前で勝負するのではなく、自分の営業スキルで戦う気構えや、さらに力を磨かなくてはという覚悟につながりました。
天野:ギャップではないですが、私の場合、求められるスキルに変化はないものの、スタメンではより“自分の意思”が求められていると感じます。
例えばルールやオペレーション部分です。前職ではその多くがきちっと決められていて、そのルールやオペレーションにより、安定して成果を生み出し続けられています。一方スタメンでは状況に応じて変化させてきたことが多いと感じます。どちらが良い悪いではないですが、会社を良くしたいという自分の意志さえあれば「それって変じゃない?」「こうした方がもっと良くなる」と言える環境は貴重だと感じます。
高原:同感です。手を挙げた個人に任せてもらえる文化が根付いていると思います。改善したいという思いでチャレンジがしやすい環境ができていると思います。
天野:「お客様に迷惑をかけない」「組織がより良くなるため」といったことであれば、どんどんやって良いと後押しをしてくれる文化がありますよね。でも、任せてもらえるからこそ同時に、自分が言ったことに対してどこまでコミットできるかも問われます。
阿部:そうですね。営業は日々細かな新しいことが起こるので、全員がオーナーシップを持って動かないと回らないです。「これやってみます」と個人で動いたものを他のメンバーが行ったことを合わせて改善し続けています。各自が自分のタスクを自分で作って、皆と併せて組織的な動きが出来上がっている。そうしなければならないと皆が理解して動いていると感じます。
高原:失敗しても挑戦したことはちゃんと讃えてくれる文化があることに驚きました。成果には目に見えるものと見えないものがありますが、スタカネ(※)やサンクスカードでどちらも見える化している点が前職と違う点で、スタメンの良い仕組みだと思っています。
目標を達成した時にみんなで盛り上げることでいい相乗効果が生まれている。何よりもそんな空気をみんなで作り上げているのが素敵だし、僕自身とても刺激を受けています。
阿部:でも僕は最初、そういった人を称賛する文化というのに戸惑いましたね。前職ではなかったし、ここまでやるんだとびっくりしました。
天野:私も最初は、「おめでとう」という言葉をみんながよく口にするので驚きました。昇進などであれば分かるのですが、例えば私の所属するカスタマーサクセス部だと、1万円の受注でも「おめでとう」と声をかける。数千円の場合もあるのだけれど、金額に関わらず、その案件が当事者にとって素晴らしいことであれば、みんなが「おめでとう」って言うんですよね。
高原:知っている人だけでなく、TUNAGの投稿で「おめでとう」と言われたり、廊下ですれ違った時に言葉を掛けてもらったりして、確かに最初はギャップを感じていました。良い意味のギャップですけれどね。
※スタメンの全オフィスに設置されている鐘。喜ばしいことがあれば、メンバーが集まって鐘を鳴らす。
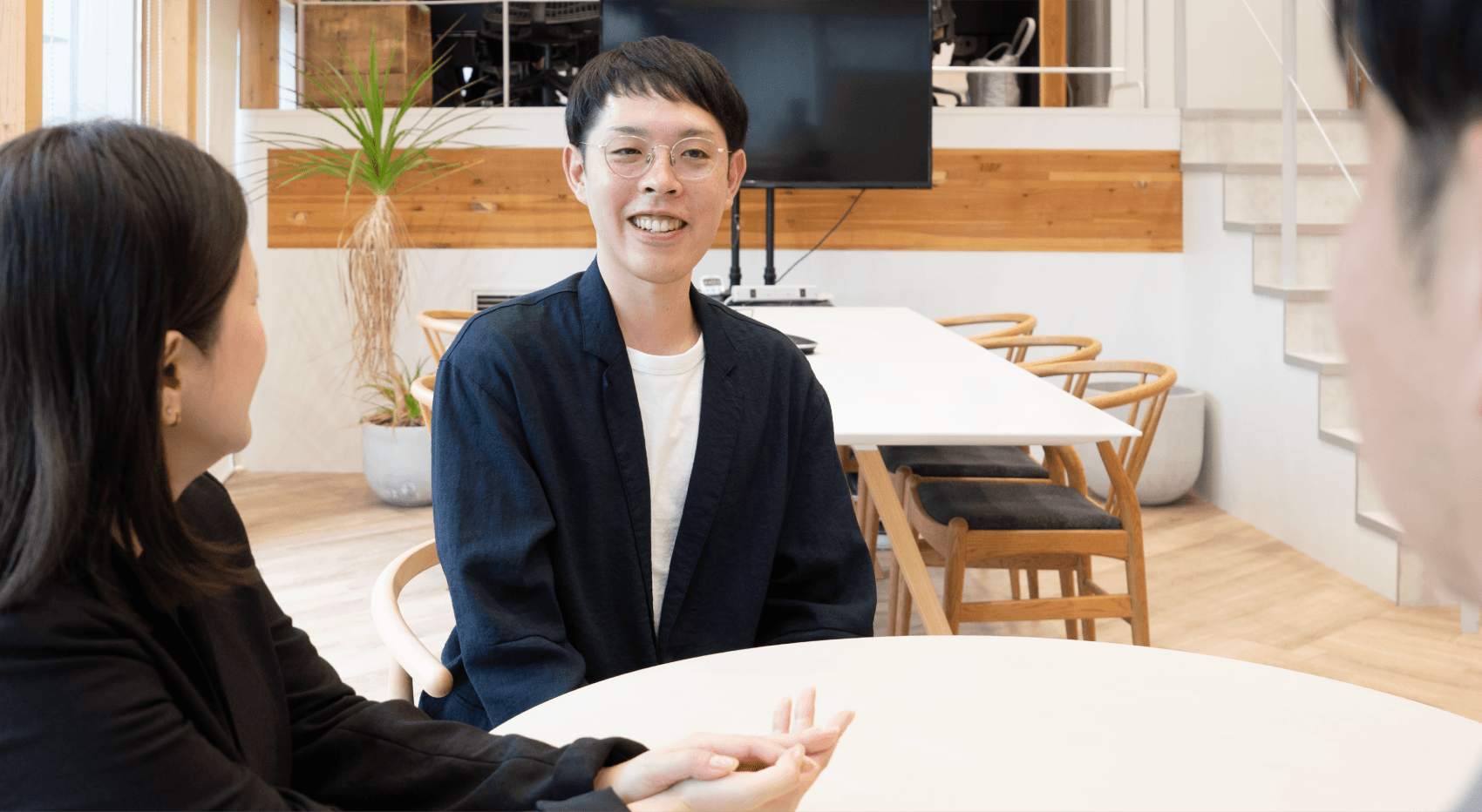
高原:自分が「こうありたい」「こうしたい」と考えたことを周囲と相談しながら進める力が身に付いたと思っています。相談するといろいろな人が、会社にとって最適なポイントはどこかというのをフィードバックしてくれるんです。そこから自分なりに目標を立てて、段取りよく進められるようになったのは新しいスキルかもしれません。
具体的な体験で言うと、入社早々、前職では経験したことのない法定開示を任せてもらいました。実は面接で「やりたい」と伝えていたので、考慮してもらえてすごくうれしかったのを覚えています。
阿部:“社員のありたい姿”というのに寄り添ってくれるというのは同感です。僕は入社した際、営業部付けではありましたが所属部は確定していませんでした。法人営業が主なグループと輸入中心のグループ、その2つを1、2週間をかけて体験し、最終的にどちらが良いかと僕に意見を求めてくれたんです。
部長の考えも伝えてもらいつつ「将来なりたい姿を描いた時にどちらをやりたいか」と問われました。当時僕に明確な答えがなかったので、「では1年後はどうか」と部長が一緒に考えてくれて、結果現在の1グループを希望しました。実際に入社したら希望どおりの配属で驚きましたね。
天野:それで言うと私も、今まさにチャレンジ中のことがあります。現在、カスタマーサクセスの部長ではありますが、同時に開発側も兼務しているんです。これは私の上司から見ると、全く違う領域の仕事を兼務することで本来のバリューが発揮できないリスクがある。それでも私の「挑戦したい」という気持ちを受け止めて、私のチャレンジ力をさらに鍛えるよう後押ししてくれた。素晴らしいなと思っています。
阿部:何かしらの意志を持っている人ですね。特に営業は、自分の売上が組織の売上に与えるインパクトが大きいので、自分の「コミットするぞ」という強い意志がないとスタメンの中では動けないと思います。称賛や許容といった優しい文化と同時にベンチャーの厳しさもあるので、しっかりとした意志を持っている人と一緒に働きたいです。
天野:加えて、困難を楽しめる人。困難は“難しい”にフォーカスすると“辛い”だけになってしまうけれど、反対に、周囲や上司の助けがある中で「まずやってみる」ということが楽しい、面白いと思える人なら、スタメンではどんどん前に進めると思います。
高原:分かります。改善できる部分が多いということは、それだけ自分が携われるチャンスが多くあるということ。スタメンは上長と話し合いができる時間も多く設けられているので、短期で目標を少しずつ改善でき成果が見えやすい。僕はそれがモチベーションにつながっていますね。
挑戦したい・改善したいことについて、スタメンでは意見交換をする場面が多いので、そういう意味でも、しっかり人に向き合って、自分はこういうことを課題に思っていると話せる人がスタメンに向いていると思います。